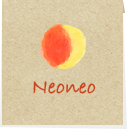知らないことだらけ!「麻の話」
「日本の麻は高級過ぎて使えない!!」
もともと麻織物は庶民のもの
麻の着物といえば最高級の織物としてあこがれを抱く女性は多く、いつか夏に麻の着物や帯をサラッと着て、日傘と真っ白な麻の足袋で涼しげに歩いてみたいと夢見たりしているのでは? しかし最近は、ハンカチやタオルという日用品にいたるまで麻製品が復活しつつある。天然素材の中でも吸湿性、吸水性に優れ、殺菌効果も高い麻は、もっとも日本の風土に合った繊維だからだ。
じつは終戦まで、麻は日本各地のいたるところで栽培され、庶民の衣食住を支える、稲に次いで欠かせぬ作物だった。 それが、こんなに稀少な高級品となってしまったのは、戦後、栽培が禁止されたからだ。
意外と知らないのが、日本の麻は「大麻」という植物で、それは「たいま」と呼ばれ、麻薬の大麻、つまりマリファナがとれる植物だということ。だから戦後、栽培が禁止されてしまったのだ。
繊維用と麻薬用ではまるで違う
日本ではおもに、大麻の茎部分の皮を剥がして繊維にし、布だけでなく紙、畳、壁材など生活全般に利用してきた。
また、お盆のとき〝おはしぎ(お箸木)〟と呼び牛や馬の足にしたりお霊供膳のお箸にしたりした、あの懐かしい「おがら」は、皮をむいた後の大麻の芯を乾燥させたものだ。七味唐辛子に入っている、あの黒くて丸い粒は大麻のタネ。鳥の餌の中に入っているのも見たことがあるだろう。
では、マリファナは大麻のどこを使って作るのか。麻薬成分であるTHCという物質は花の雌しべに含まれる。葉を煙草のように巻いて吸う人たちもいる。
戦後の栽培禁止にあたり、野州麻の産地として知られた栃木県だけが大麻の栽培を許された。その後、栃木県農業試験場は「産業用大麻」というTHC成分のない大麻を育種した。これならマリファナは精製できない。
「麻ってリネンやケナフとは違うの?」
植物としてはまったく違う種類の麻たち
一口に麻といっても、世界中にはさまざまな麻織物の原料がある。
ヨーロッパ製の高級な麻というイメージで日本人女性に人気の高いリネン。日本では「亜麻」と呼ばれるアマ科の一年草だ。よく「からむし」と呼ばれるのが「苧麻」というイラクサ科の多年草で英名を「ラミー」という。「黄麻」は英名の「ジュート」の名の方が知られているシナノキ科の一年草。「マニラ麻」は英名「アパカ」というバショウ科の一年草。「ケナフ」は日本名で洋麻と呼ばれるアオイ科の一年草だ。
そして日本の麻は「大麻」というアサ科の一年草で英名をヘンプという。マリファナになるTHCがなぜ大麻にだけ含まれるのかというと、植物としてはどの麻も科が違うまったく別の種類で大麻だけがアサ科だからである。いずれも茎から繊維をとって織るところから麻と総称されたのかもしれない。
麻織物は風通しがよく熱を逃がす性質があるため、夏の衣服や寝具にふさわしいとされるが、他方、繊維の中に空気を含むためサーモタット機能があり、冬は温かくて一年を通して使いこなせる。
使えば使うほど柔らかく心地よさ抜群の大麻
中でも日本の麻、大麻は、特に優れた性質をもつ繊維だ。
使いこなすほどに柔らかくなり、年を重ねた大麻はコットンのような肌ざわりになる。しかし洗いたては新品のように張りが戻るので、汗ばむ季節に袖を通すときの心地よさは抜群である。
また天然のUVカット機能も備えているので、紫外線から肌を守ってくれる。調湿作用に優れ、汗ばんでも肌に張りつかず、すぐに乾く上に、天然の抗菌性にも優れているため、汗による臭いなども軽減される。
高温多湿の日本にぴったりの麻は、戦前までは日本のいたるところで女性たちが栽培し、糸を紡ぎ、家族の衣類に仕立てたり、売って家計の足しにしていたと言われる。そんな、日本女性が長い時を経て育んできた伝統文化が、戦後のわずか70年で単なる麻薬としてしか扱われない存在になってしまったのだから悲しい。
「なぜ国産の麻がないの?」
万が一の危険回避で栽培を禁止
日本でただ一県、栽培が許された栃木県は、マリファナにはならない産業用大麻を育種したにもかかわらず、そのタネを勝手に他県へ譲ることを禁じられている。
植物は、交配を重ねて新品種をつくっても何世代か続くと〝先祖がえり〟といって、交配前の原種に戻ってしまうことがある。栃木県外に譲ったタネがしっかり管理されていないと、やがて先祖がえりでTHC成分のあるタネが生まれてしまうかもしれない、そのわずかな危険を100%排除するための予防措置なのだ。
そして、産業用大麻のタネを使って繊維をとる目的だけで栽培をしようと思っても、盗まれる危険を100%排除するために、ほとんど認可されることはない。これも、たとえば大麻畑から盗んだ葉を挿し木して育て、万が一でも先祖がえりしてマリファナができるようなことがあってはならないという予防措置なのである。
こうした厳しい認可制度と繊維産業の衰退で、いつしか麻栽培は日本から消えてしまったのだ。
消費者の意識が高まれば危険回避はできる
いま、中国製の食品に不安を抱く人は多い。しかし中国への依存度が高い繊維産業も似たような状況だ。布だって直接肌に触れるものだから、できることなら国内産を使いたい。
とくに日本古来の優れた繊維である麻は、これから海外にアピールできる産物にもなれるのだから、少なくとも日本人なら国内産の麻を身につけたいものだ。自分が暮らす地域で、目に見える畑で、目に見える農業で栽培された麻を身につける。戦前までごく当たり前だった暮らしを、なぜ取り戻せないのだろうか。
たしかにドラッグの乱用は防ぎたい。しかしマリファナにならない麻の栽培まで禁じることが果たして歯止めになるのだろうか。
それよりも、なるべく多くの消費者が地元産の麻栽培を見て、産業用大麻という品種への理解を深めることの方が効果的なのではないだろうか。なぜなら、日本人の暮らしを支えてきた大麻という畑の作物は優れた繊維をとるためのもので、決してマリファナをつくるものにしてはいけない、という意識が浸透しやすいからだ。